KUMA’S FUSION ROOM


KUMA’S FUSION ROOM

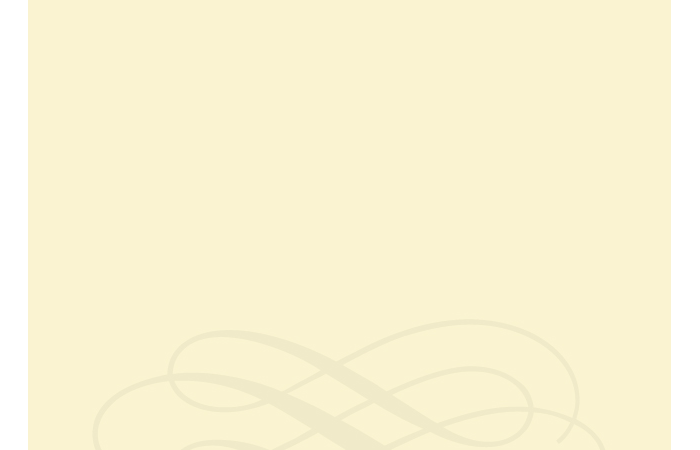
フュージョンの歴史(日本編)
ロック・フィールドから始まったジャパニーズ・フュージョン
日本のフュージョン・シーンの歴史を紐解いてみると、アメリカとはちょっと違った発展のしかたをしているということがわかる。アメリカでフュージョンが 盛り上がり始めていた70年代の中盤から、日本でもフュージョン的なサウンドを自分の音楽に積極的に取り入れるミュージシャンたちが登場してきたが、その 多くはロック・フィールドで活躍しているミュージシャンたちだった。そしてそういった動きと、ジャズ・フィールドのミュージシャンたちとの“異種交流” が、初期のジャパニーズ・フュージョンを作り上げていったのである。もちろん“ジャズ・ミュージシャン”たちも、例えば渡辺貞夫は69年の『パストラル』 からいわゆる“ジャズ”を超えた音作りを試みていたし、菊池雅章や川崎燎なども当時から独自のサウンドをクリエイトしていた。だが70年代前半、日本の音 楽シーンにフュージョン的なサウンドを積極的に取り入れていたのは、ロック・フィールドのミュージシャンたちが圧倒的に多かったのである。
74年には井上陽水が『二色の独楽』でデヴィッド・T・ウォーカーやハーヴィ・メイソンなどと共演して話題を呼んだし、サディスティック・ミカ・バンド や、ティン・パン・アレイ(吉田美奈子や山下達郎なども含む)、四人囃子などは当時からフュージョン的なサウンドを巧みに彼らの音楽に取り入れていた。 ティン・パン・アレイの『キャラメル・ママ』(75年)の「チョッパーズ・ブギー」は日本フュージョン黎明期の名演として名高いし、四人囃子の『ゴールデ ン・ピクニックス』(76年)の「レディ・ヴァイオレッタ」は個人的には日本フュージョン史に残る名曲だと思っている。あとリトル・フィートやタワー・オ ブ・パワーのメンバーたちとレコーディングされた鈴木茂の名作『バンド・ワゴン』(75年)も忘れ難い。また75年には林立夫、小原礼、ジョン山崎、村上 “ポンタ”秀一、大村憲司、浜口茂外也による“バンブー”(76年に小原、村上、大村、是方博邦による“カミーノ”に発展)が結成され、深町純も“バン ブー”のメンバーたちを中心とした“21st・センチュリー・バンド”で活動していたほか、ブレッカー・ブラザーズとの共演盤などもレコーディングしてい る。また大阪にも“浪速のスタッフ”と呼ばれたベイカーズ・ショップがあった。またミカ・バンドから発展した“サディスティックス”(高中正義、今井裕、 後藤次利、高橋幸宏、斉藤ノブ他)もさらにフュージョン色の強まったサウンドを展開していた。
ジャズ・シーンの動き
そういった動きを受け、ジャズ・フィールドで活動していたミュージシャンたちが自分たちのサウンドに積極的にフュージョン・サウンドを取り入れるように なっていったのは、77年頃からである。77年8月、ニューヨークの“セヴンス・アヴェニュー・サウス”やロサンゼルスの“ベイクド・ポテト”に匹敵する ジャパニーズ・フュージョンの“拠点”六本木ピットインがオープンし、ジェントル・ソウツの来日公演で超満員となる。そしてこのあたりから日本のフュー ジョン・シーンもイッキに盛り上がっていった。この年レコーディングされた作品には渡辺貞夫の『マイ・ディア・ライフ』(JVC/フライング・ディス ク)、増尾好秋の『セイリング・ワンダー』(エレクトリック・バード)、渡辺香津美の『オリーヴス・ステップ』(ベター・デイズ)などがある(あと、その 前年の76年にリリースされた笠井紀美子の『フォール・イン・ラヴ』も忘れ難い)。この3作品はその後のフュージョン・シーンに大きな影響を与えた。ロサ ンゼルスでレコーディングされた『マイ・ディア・ライフ』、ニューヨークでレコーディングされた『セイリング・ワンダー』は、日本人ミュージシャンの実力 が海外でも十分に通用するということを証明していたし、『オリーヴス・ステップ』では渡辺香津美と坂本龍一が出会い、後の“カクトウギ・セッショ ン”“KYLYN”の原点となった。また3作品の“JVC/フライング・ディスク”“エレクトリック・バード”“ベター・デイズ”というレーベルは、ジャ パニーズ・フュージョンの3大レーベルとしてシーンをリードしていくようになる。さらにライヴ・アンダー・ザ・スカイが始まったのも77年からだし、渡辺 香津美、大村憲司、森園勝敏、山岸潤史という4人のギタリストが共演し、ギター・ブームの火付け役となった『ギター・ワークショップ』や、笠井紀美子の初 の日本語アルバム『トーキョー・スペシャル』がレコーディングされたのもこの年だった。
そして78年から79年にかけて、渡辺貞夫の『カリフォルニア・シャワー』、日野皓正の『シティ・コネクション』、ネイティヴ・サンのデビュー・アルバ ムなどが次々と大ヒットを飛ばし、ジャパニーズ・フュージョンも大いに盛り上がっていった。当時はあの“ミュージック・フェア”にまで渡辺貞夫とジェント ル・ソウツが出演したり、また渡辺貞夫(資生堂)、日野皓正(サントリー)、ネイティヴ・サン(マクセル)などがテレビCMに出演し、お茶の間まで彼らの 顔と音楽が浸透するという、今ではちょっと考えられないような現象も起こっていたのである。
そして、KYLYN登場
そういった動きを受け、79年、渡辺香津美、坂本龍一、矢野顕子、村上“ポンタ”秀一、清水靖晃、本多俊之、向井滋春、小原礼などといった、渡辺貞夫、 日野皓正に続く世代の若者たちが集まり、伝説の“KYLYNセッション”が誕生し、一大センセーションを巻き起こした。また“伝説”のニューヨーク・オー ルスターズの日本ツアーもこの年だ。そしてザ・スクェア(現T-スクェア)、カシオペア、松岡直也&ウィシング、プリズム、ネイティヴ・サン、 ザ・プレイヤーズ、佐藤允彦&メディカル・シュガー・バンク、パラシュート、バーニング・ウェイヴ、キープ、モーニング・フライト、さらに“浪速 フュージョン”と呼ばれたナニワ・エキスプレス、99.99、羅麗若などといった新しいグループも次々と登場し、ジャパニーズ・フュージョンも活況を呈す るようになっていった。おっとスペクトラムとYMOのデビューも忘れちゃいけない。特にYMOの出現は、その後の日本の音楽シーンを根底から覆した“事 件”だったし、渡辺香津美、橋本一子、大村憲司などといったフュージョン系ミュージシャンも彼らのツアーなどに参加していた。そして翌80年には渡辺貞夫 が武道館でコンサートを開き、渡辺香津美のニューヨーク録音盤『TOCHIKA』が空前のヒットを記録する(テレビのCMにも登場しました)など、ジャパ ニーズ・フュージョンも最大の盛り上がりを見せていったのである。
また同じく80年には、清水靖晃、笹路正徳、土方隆行、山木秀夫などによる“マライア”が『エン・トリックス』でデビュー。彼らを中心とした“ファミ リー”でありとあらゆる音作りに過激にチャレンジし、笹路正徳の『ホット・テイスト・ジャム』、土方隆行の『スマッシュ・ザ・グラス』、清水靖晃の『ベル リン』などといった“早すぎた名作”を次々と送り出していった。また彼らは渡辺香津美と合体して“KAZUMI BAND”となり、『頭狂奸児唐 眼』(81年)、『ガネシア』(82年)という、これまた“早すぎた名作”を誕生させている。またその頃から生活向上委員会大管弦楽団、Wha-ha- ha、はにわオールスターズ、近藤等則チベタン・バンド、カラード・ミュージックなどといった、日本という土壌からしか絶対に生まれてこないようなユニー クな“フュージョン・グループ”も登場する。これらはKYLYN、YMOを“体験”した後だからこそ登場し得たグループだといえるかもしれない。テクノロ ジーを駆使し、日本人の感性とポップ感覚を持ったそれらのグループは、まさに日本音楽界の“偉大なる突然変異”だった。そして同じような“突然変異”とし て、45回転LPのみをリリースするという“Shan-Shan”レーベルも登場し、『パダング・ルンプット/村上“ポンタ”秀一』(名作!)『インスタ ント・ラスタ/ペッカー』『うたかたの日々/マライア』などといったユニークな作品をリリースしていった。
日本フュージョンの変容
そのような動きを受けて、83年年頃から日本のフュージョンもその形態が徐々に変わっていった。渡辺貞夫の『フィル・アップ・ザ・ナイト』がアメリカ “ラジオ&レコード”誌のジャズ・チャートで1位を記録し、またこの年MALTAが登場するなど、ポップなものはよりポップな方向に進むようにな り、一方で渡辺香津美の『MOBO』や清水靖晃の『北京の秋』などといった、より“深い”サウンド・メイキングやインタープレイを目指す方向性もででき た。そしてポップ・インストゥルメンタル傾向はT-スクェアとカシオペアを中心に、より綿密なアンサンブル/アレンジと耳当たりのいいメロディを前面に押 し出すようになり、インタープレイ傾向は渡辺香津美をはじめとする“MOBO倶楽部”のメンバーなどを中心として、より自由な方向性へと発展していった。
だが当時日本のジャズ・シーンを囲む状況は底冷え状態にあり、アルバムのリリース数、ライヴの動員などいずれも減少傾向にあった。彼らはそんな中で、地 道な活動を続けていたのである。そして日本のフュージョン・シーンが再び盛り返すようになるには、T-スクェアが『トゥルース』をリリースし、本多俊之ラ ジオクラブが「ニュース・ステーション」「マルサの女」などのテーマを担当し、チキンシャックやノブ・ケインなどといった新グループが登場してくる87年 以降まで待たねばならない。
(text by Yoshihiro "KUMA" Kumagai)
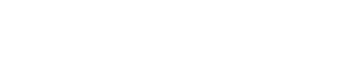
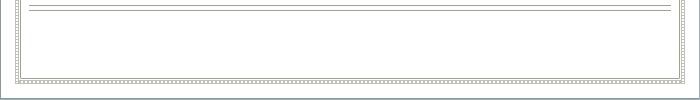
ⓒ 熊谷美広 (Yoshihiro Kumagai)