KUMA’S Fusion Room


KUMA’S Fusion Room

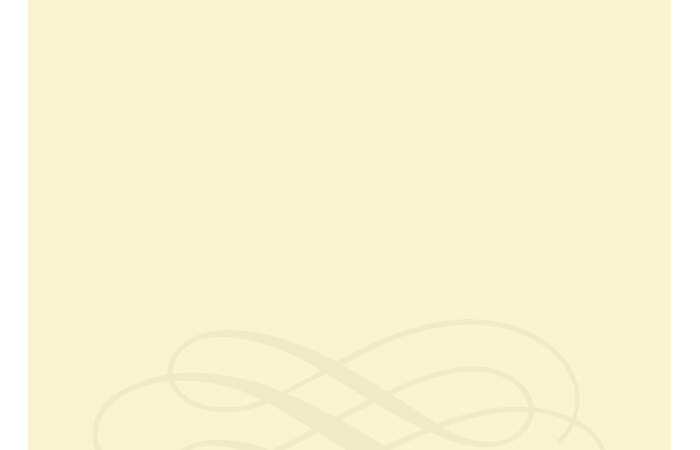
フュージョンの歴史(海外編)
フュージョン黎明期
フュージョンという音楽は、その名の通り“融合”の音楽である。フュージョンはジャズとロックを中心に、様々な音楽の要素を取り入れて発展してきた。スタイルとしては、リズムとメロディをロック/ポップスから、そしてハーモニーとインプロヴィゼイションをジャズから取り入れた音楽が、今日フュージョンと呼ばれている音楽の基本的なフォーマットだといえるだろう。では、そのような音楽がどのような状況から生まれてきたのか、そして現在の音楽シーンとどのようにつながっているのか、ということを中心に話を進めていこうと思う。
そもそもフュージョンという音楽の歴史は60年代の後半から始まる。当時ジミ・ヘンドリックス、ジェイムス・ブラウン、スライ&ファミリー・ストーンなどといったミュージシャンの音楽に心酔していたジャズのオピニオン・リーダー、マイルス・デイヴィスは、自分の音楽に彼らの音楽の要素を取り入れることを思いつく。そして『イン・ザ・スカイ』や『イン・ア・サイレント・ウェイ』などといったアルバムでエレクトリック・サウンドやファンク・ビートを大胆に取り入れ、新しいサウンドを模索していった。そして彼はさらにジャズが60年代から取り入れていたポリリズム(これはアフリカン・ミュージックからの影響だ)の要素も加えて、69年に画期的な大作を作り上げた。それが『ビッチェズ・ブリュー』である。つまりここでロックとファンクとジャズとアフリカン・ミュージックが出会ったわけだ。そしてここでひとつ忘れていけないのは、そのすべてがブラック・ミュージックであったということである(ジミ・ヘンドリックスが黒人であったことを思い出そう)。つまりマイルスによるフュージョンはブラック・ミュージックのフュージョンだったのである(これは彼が死ぬまで実践していたことだ)。そして当時のマイルス・バンドから輩出されたハービー・ハンコック、チック・コリア、ジョー・ザヴィヌル、ウェイン・ショーター、トニー・ウィリアムス、ジョン・マクラフリン、ビリー・コブハムなどが、マイルスから学んだ方法論をそれぞれ独自の解釈で展開し、“マイルス流フュージョン”を発展させていったのである。特にジョー・ザヴィヌルとウェイン・ショーターの“ウェザー・リポート”、チック・コリアの“リターン・トゥ・フォーエヴァー”、ハービー・ハンコックの“ヘッド・ハンターズ”の3グループは、70年代前半のフュージョン・シーンの中心グループとして活躍していくことになるのである。またトニー・ウィリアムスの“ライフタイム”、ジョン・マクラフリンの“マハヴィシュヌ・オーケストラ”なども当時は大きな注目を集めた。
こういうことからマイルスを“フュージョンの生みの親”とするジャーナリズムも多いが、それは部分的な見解でしかない。たしかにマイルスはフュージョンのひとつの流れを作り出したが、それはあくまでも“ひとつの流れ”にしかにすぎないのである。
マイルスとならんで、60年代の後半に、フュージョンの原形を作り出したもうひとりの男がいる。プロデューサーのクリード・テイラーだ。60年代にヴァーヴ・レーベルでボサ・ノヴァを世界的にヒットさせた彼は、67年にA&Mに移籍、CTIレーベルを設立し、ウェス・モンゴメリーの『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』を制作した。ジャズ・ミュージシャンとオーケストラが共演し、ポップ・ソングを演奏するというこのアルバムは当時“イージー・リスニング・ジャズ”と呼ばれ、“真面目な”ジャズ・ファンからはソッポを向かれたが、一般的には大ヒットし、このコンセプトは今日のフュージョンのひとつの原点となっていった。そして70年にCTIは独立し、インディペンデント・レーベルとしてスタートする。またクリード・テイラーはブラック・ミュージックを基本としたレーベル“KUDU”も設立し、CTIとKUDUから、今でいうフュージョンのアルバムを次々とリリースしていった。そうして生まれたのが『春の祭典/ヒューバート・ロウズ』『ミスター・マジック/グローヴァー・ワシントン・Jr.』『シュガー/スタンリー・タレンタイン』『ツァラトゥストラはかく語りき/デオダート』などといったヒット・アルバムであった。またCTIの作品にはオーケストラが参加した作品も多く、そういった環境の中から、ドン・セベスキーをはじめとして、デオダート、ボブ・ジェイムス、デイヴ・グルーシン、デヴィッド・マシューズ、クラウス・オガーマン、ラロ・シフリンなどといったフュージョン・シーンを代表する有能なアレンジャーも育っていったのである。
ブラック・ミュージックからのフュージョン
だが、フュージョンの原点はマイルスとCTIだけではない。ちょうど同じ頃、モータウンやアトランティック、スタックスなどといったR&Bのスタジオからもフュージョンの胎動が始まっていたのだ。マーヴィン・ゲイ、スティーヴィー・ワンダー、ダニー・ハザウェイ、ロバータ・フラックなどといったシンガーたちはバックにジャズ系のミュージシャンを好んで使い、新しいR&Bサウンドをクリエイトしていた。そしてそういったミュージシャンのアルバムに参加していたスタジオ・ミュージシャンたちがレコーディングの合間にセッションを重ね、独自のインストゥルメンタル・サウンドを作り出していったのである。
そんな中から生まれた、ブラック・フュージョンの原点ともいうべき存在がブッカー・T & MG'sだ。彼らはスタックス系のシンガーのバックをつとめていたが、そのインストゥルメンタル・サウンドは、今日のフュージョンの土台を築いたといってもいいのかも知れない。またそういったジャム・セッションのひとつの重要な記録が、69年にレコーディングされた『チャック・レイニー・コーリション』だ。ここにはリーダーのチャック・レイニーの他に、リチャード・ティー、コーネル・デュプリー、エリック・ゲイル、バーナード・パーディなどが参加していた(そしてもちろん、ここから生まれたのが“スタッフ”である)。またフュージョン的なアレンジをいち早く取り入れ、スタジオ・ミュージシャンを大胆にフィーチュアしたゲイリー・マクファーランド(彼はデイヴ・グルーシンや渡辺貞夫に大きな影響を与えた)の『アメリカ・ザ・ビューティフル』もフュージョンの先駆けともいうべき作品となった。
そしてそういったスタジオ・セッションの流れをひとつにまとめ、壮大な作品を完成させたのがアレンジャー/プロデューサーのクインシー・ジョーンズだ。彼が69年に制作した『ウォーキング・イン・スペース』(この作品もCTIレーベルだ)には『チャック・レイニー・コーリション』『アメリカ・ザ・ビューティフル』の主要メンバーのほか、ボブ・ジェイムスやヒューバート・ロウズなども参加していた。ここではジャズとR&Bが見事に解け合い、これまでにはなかった独自の音世界を作り出していた。やはりクインシーもフュージョンの生みの親のひとりなのである。しかもここで行なわれていたのも“ブラック・ミュージックの再構築”だった。つまりマイルスやクインシーは彼らなりの方法論で、様々なブラック・ミュージックの要素をひとつにまとめようとしたのである。こういったアプローチは後のクインシーの『バック・オン・ザ・ブロック』などにそのまま引き継がれているし、また形こそ違うが現在のプリンスなどとも同じ発想である。つまりよく言われるような商業主義ではなく、そういうアグレッシブなアプローチから生まれてきたのがフュージョンという音楽だったのである。
そしてもうひとり忘れていけないのはキング・カーティス。サム・クックやアレサ・フランクリンとも共演していた彼は、サックスによるR&Bインストゥルメンタルという、まさに今のフュージョンの原点ともいうべき音楽を展開していた人で、『ウォーキング・イン・スペース』などの参加ミュージシャンたちをはじめとして、マイケル・ブレッカー、デヴィッド・サンボーン、スティーヴ・ガッドなどに大きな影響を与えた人物である。最近サンボーンがキング・カーティスの曲を取り上げたりして、彼の再評価の気運が高まって入るが、その後の音楽シーンに与えた影響度はマイルスやクインシー、クリード・テイラーなどに優るとも劣らない、重要な人物なのである。
そして、いよいよフュージョン誕生へ
そしてちょうど同じ頃(60年代後半~70年代前半)、ジャズ・グループ“ジャズ・クルセイダーズ”がブラック・ミュージシャンとしてのアイデンティティをより明確にするために、自分たちの音楽にブラック・ファンクの要素を大胆に取り入れ、ついにはグループ名から“ジャズ”を取り去り、“クルセイダーズ”としてスタートする。また当時からジャズ、ブルース、R&Bからレゲエやカリプソまで、あらゆるブラック・ミュージックの要素を融合し、独自のサウンドをクリエイトしていた“早すぎたグループ”ウォーが登場したのもこの頃だ。あとハービー・マンは『メンフィス・アンダーグラウンド』でメンフィスのR&Bミュージシャンと共演し、フュージョンの原点のような演奏を展開していたし、このアルバムに参加したラリー・コリエルのロックの手法を取り入れたギターやロイ・エアーズのプレイなども話題となった。あとチャールス・ロイドも60年代後半からロック的なサウンドを取り入れた音楽を展開していた(彼のグループにはマイルス・バンド参加前のキース・ジャレットとジャック・ディジョネットがいた)。
さらに白人のスタジオ・ミュージシャンたちも、新しい音楽を模索して、様々なセッションを重ね、独自のサウンドをクリエイトしていった。その記録が『ホワイト・エレファント』だ。このアルバムはマイク・マイニエリが中心となり、ランディ&マイケル・ブレッカー、ロニー・キューバー、スティーヴ・ガッドなどが参加していた。またその『ホワイト・エレファント』の精神を引き継いだのが、ブラッカー兄弟、ウィル・リー、ビリー・コブハム、ジョン・アバークロムビーなどによる“ドリームス”である。
またロック・シーンにおいても、キング・クリムゾン、ピンク・フロイド、クリーム、EL&P、ソフト・マシーンなどが逆にジャズの要素を取り入れたロックを展開し、話題になったのもこの頃だ(こういったシーンから輩出されたのが、現在ジャズ・シーンでも活躍しているアラン・ホールズワース、ビル・ブラッフォード、パーシー・ジョーンズなどといったミュージシャンである)。おっと、サンタナやタワー・オブ・パワーなどといったサンフランシスコ出身のロック畑のミュージシャンたちの登場も忘れちゃいけない。
このように、特定のミュージシャンがフュージョンを作り上げたのではなく、渾然としたミュージック・シーンから“時代の必然”として登場してきたのがフュージョンという音楽だったのである。だから何度もいうが、決してコマーシャルな発想で出てきた音楽ではないのである。まぁ、それが結果としてコマーシャルな成功を収めた、ということはあるが。また、エレクトリック・ベースやシンセサイザーという楽器の発達も見逃せない要素のひとつだ。
そしてウェザー・リポートのデビュー・アルバム、チック・コリアの『リターン・トゥ・フォーエヴァー』、ハービー・ハンコックの『ヘッド・ハンターズ』、ビリー・コブハムの『スペクトラム』、ジョン・マクラフリンのマハヴィシュヌ・オーケストラの『火の鳥』、クルセイダーズの『スクラッチ』、ドナルド・バードの『ブラック・バード』、コーネル・デュプリーの『ティージン』、スティーヴ・マーカスの『カウンツ・ロック・バンド』などといったフュージョン黎明期の名作が次々とリリースされていった。トム・スコットのLAエクスプレスやザ・セクションなどといった第一次スタジオ・ミュージシャン・グループの結成ブームもこの頃だ。
そして75年にはジェフ・ベックが大胆にフュージョンに挑戦し、その後の音楽シーンに大きな影響を与えた『ブロウ・バイ・ブロウ』を発表している。またウェイン・ショーターはブラジルのシンガー・ソングライター、ミルトン・ナシメントをフィーチュアした傑作『ネイティヴ・ダンサー』をリリースし、ジャズとモダン・ブラジリアン・ミュージックとの融合という新たなる可能性を提示した。そして同じく75年にはマイルスが股関節の持病が悪化し、活動を停止する。新しい流れが始まりつつあったのである。だがご存じのようにこの頃はまだ“フュージョン”という名前はなく、“ジャズ・ロック”とか“クロスオーバー”などと呼ばれていた。“フュージョン”という音楽が登場するのは70年代の後半まで待たねばならない。
ベンソンが火をつけた大ブーム
76年、この年はフュージョンにとって非常に大きな意味を持つ。まずこの年、ジョージ・ベンソンがプロデューサーのトミー・リピューマと組んであの『ブリージン』を発表する。このアルバムの大ヒットがフュージョン・ブームのきっかけを作ったといっても過言ではない。なんとビルボード誌のポップ・アルバム・チャートの1位になり、グラミー賞の3部門を獲得してしまったのである。フュージョンがついに市民権を得たのだ。そしてこの年には他にスタッフ、ブレッカー・ブラザーズのデビュー、ジャコ・パストリアスのウェザー・リポート加入、デヴィッド・サンボーン、パット・メセニー、リー・リトナー、アール・クルーの登場と、その後のシーンにダイレクトにつながる“事件”が次々と起こっている。
そして77~78年にかけてフュージョンは一大ブームとなる。スパイロ・ジャイラの『モーニング・ダンス』やチャック・マンジョーネの『フィール・ソー・グッド』が大ヒットし、ラリー・カールトンとリー・リトナーを中心としたギター・ブームが到来し、マイク・マイニエリの『ラヴ・プレイ』が発表と、まさにフュージョン花盛りの状況だった。ニール・ラーセン、ジェフ・ローバーなどといったニュー・スターやシー・ウインド、24丁目バンドなどといった新しいグループも登場してきた。またスティーヴィー・ワンダーの『キー・オブ・ライフ』やアース・ウインド&ファイアの『太陽神』、クインシー・ジョーンズの『スタッフ・ライク・ザット』、ハービー・ハンコックの『サンライト』など、フュージョンとブラック・ミュージックが新しい形で結び付くような音楽も生まれていった。さらにマイケル・フランクスの『スリーピング・ジプシー』、スティーリー・ダンの『エイジャ』、ポール・サイモンの『時の流れに』そしてジョニ・ミッチェルの『ミンガス』や『シャドウズ・アンド・ライト』などといった、ポップ・ミュージックにもフュージョンが大きな影響を与えるようになっていった。いや、フュージョンがなければAORという音楽は生まれてこなかったといっても過言ではないかもしれない。そしてそういったアルバムのセッションなどにより、それまでスポット・ライトが当たることはなかった楽器のプレイヤー、ドラムのスティーヴ・ガッドやハーヴィ・メイソン、ベースのアンソニー・ジャクソンやウィル・リー、またデヴィッド・スピノザ、ジョン・トロペイ、スティーヴ・カーンなどといったスタジオ・ギタリストたちもスターの仲間入りを果たすようになっていった。またそういった動きから、エアプレイ(ジェイ・グレイドン、デヴィッド・フォスター)やTOTO、ペイジズなどといった新しいタイプのロック/フュージョン・グループも登場するようになっていった。
そして70年代後半から80年代前半にかけて、ウェザー・リポートがジャコとピーター・アースキンというメンバーを得て頂点を極め、ブレッカー・ブラザーズが究極の傑作『ヘヴィ・メタル・ビ・バップ』を、そしてパット・メセニーが大ヒット作『アメリカン・ガレージ』を発表し、マーカス・ミラーが出現し、新しいリズムを取り入れたハーブ・アルパートの『ライズ』がヒットしと、フュージョンもいよいよ成熟期に入っていったのである。そしてニューヨークの“セヴンス・アヴェニュー・サウス”、ロサンゼルスの“ベイクド・ポテト”というフュージョンの“拠点”も盛り上がり、ここで毎夜のように、新しい音楽をクリエイトする“実験”が行なわれていったのである。いわばピ・パップ創生期における“ミントンズ”のような存在だ。
フュージョンへの反動
だが前記の76年という年にはもうひとつ重要な“事件”が起こっていた。ハービー・ハンコックの“V.S.O.P.”である。ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルのスペシャル・イベント用に結成されたハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、フレディ・ハバード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスというクインテットは大きなセンセーションを呼び、その時1回こっきりの予定だったのが(“V.S.O.P.”とは“Very Special Onetime Performance”の略だ)、あまりの反響の大きさにレギュラー・グループ化し、その後ワールド・ツアーを行なうまでになる。そしてフュージョン・ブームを好ましく思っていなかった“ジャズ・ファン”はこれに飛びついた。そして“ジャズの復権”を叫び出すのである(“ニューズ・ウィーク”誌はV.S.O.P.を表紙にし、“Jazz Comes Back”なんていう企画まで組んだりした)。そしてこれが80年代に入って、大きな流れとなっていくのである。
81年、音楽シーンに突然ウィントン・マルサリスが登場する。“ジャズの復権”をのぞむファンたちは彼をジャズの救世主としてまつりあげ、それが大きなムーブメントとなり、“80年代はアコースティック・ジャズの時代だ”という風潮を作り出していった。
そして同じ頃フュージョンという音楽自体も変化しつつあった。そのきっかけとなったのがクルセイダーズの『ストリート・ライフ』、グローヴァー・ワシントン・Jr.の『ワインライト』、リー・リトナーの『RIT』などのヒットである。その3枚ではヴォーカルが大きくフィーチュアされ、“インストゥルメンタルとしてのフュージョン”というものの形が変わりつつあることを示唆していた。それは70年代後半に起こった、アメリカのレコード業界の空前の不況にも原因がある。つまりレコード会社はレコードのセールスに直接つながるラジオのオン・エア率を上げるために、フュージョン系のアルバムにもヴォーカル曲を入れることを強制し始めたのである。その結果としてヴォーカル入りのアルバムが一気に増えたわけであるが、真にクリエイティヴなミュージシャンはそれを逆手にとり、前記のような素晴らしいアルバムを作り上げていった。だがそのときに“失敗”してしまってミュージシャンや、レコード会社から契約を打ち切られてしまったミュージシャンが多かったのも事実である。
また当時は『サタデイ・ナイト・フィーヴァー』がきっかけとなったディスコ・ブームの真っ最中であり、そちらのほうに流れていったミュージシャンたちもいた。クインシー・ジョーンズは『愛のコリーダ』をヒットさせ、ジョージ・デュークは「シャイン・オン」をディスコでヒットさせ、ハービー・ハンコックは『ライト・ミー・アップ』という100%ディスコともいうべきアルバムを発表し論議を呼んだ。だがもともとディスコ・ミュージックはダンスのための音楽であるため、クインシー・ジョーンズやジョージ・デューク、ハービー・ハンコックをしてもそれ以降あまり発展させることができず、こちらの方向性は袋小路に入ってしまうことになる(クインシーはマイケル・ジャクソンのプロデュースに行ってしまう)。どちらかといえば、シャカタクやレヴェル42などといった、イギリスから登場してきたフュージョン・グループのほうが、ダンス・ミュージックの要素を取り入れるのはうまかったかもしれない。そしてこのあたりから“フュージョン・ブーム”も陰りを見せ始めるようになる。
また、それ以外にもウェザー・リポートは自分たちのサウンドに4ビートを大胆に導入し、『ナイト・パッセージ』『ウェザー・リポート』で頂点を極め(『ナイト・パッセージ』ではデューク・エリントンの「ロッキン・イン・リズム」を取り上げていた)、マイク・マイニエリやマイケル・ブレッカーたちはセヴンス・アヴェニュー・サウスのセッションから“ステップス”を結成し、これまた4ビートのアコースティック・ジャズをプレイした。チック・コリアがマイケル・ブレッカー、スティーヴ・ガッド、エディ・ゴメスというカルテットで『スリー・カルテッツ』というアコースティック・ジャズ・アルバムを作ったのもこの頃だ。またパット・メセニーは“パットが考えるジャズ”ともいうべき『80/81』を制作し、またブラジル音楽を自分のサウンドに取り入れるなど、フュージョンという音楽そのものが拡散していったのである。
そして最近のバンド・ブームがいとも簡単に終わってしまったように、フュージョン・ブームも終りを告げる。“ブーム”というものはいつかは終わるものなのだ。
フュージョンは死なず
だがフュージョンは死ななかった。人によっては(特にジャズ・ジャーナリズムに携わっている人々)“もはやフュージョンという音楽は終わった”などと言っている人もいるが(そういうヤツに限ってフュージョン・ブームの時には“フュージョンこそこれからの音楽だ”なんて言ってたんだよね)、フュージョンという音楽はどんどん新しい音楽の要素を取り入れ、しぶとく生き残り、そして結果的に、コンテンポラリー・ジャズのひとつのジャンルとして発展していくことになるのである。
またこの頃テクノロジーの進化もあり、ミュージシャンたちは様々な“実験”を行なっている。パット・メセニーはデジタル・シンセサイザー“シンクラヴィア”とギターとをつないでそのギター・サウンドの幅を大きく広げたし、ハービー・ハンコックは同じくデジタル・シンセの“フェアライト”を使い始めた。ジョー・ザヴィヌルは『ドミノ・セオリー』でドラム・マシンに基本的なリズムを担当させ、その上でドラマーのオマー・ハキムに“インプロヴィゼイション”をさせるという、器械の弱点を逆手にとった手法に挑戦している。またマイケル・ブレッカーはサックス・シンセサイザー“EWI”(当時は“スタイナー・ホーン”と呼んでいた)を導入し、そのサウンドをさらに多彩にしていった。またリー・リトナーやアラン・ホールズワースは“シンタックス”というギター・シンセサイザーに挑戦している。そしてこういった様々な実験が、のちのフュージョン・シーンに大きな成果となって残っていくのである。その典型的な例がハービー・ハンコックの『フューチャー・ショック』だ。ハービーはこのアルバムで先進的なミュージシャン集団“マテリアル”(ビル・ラズウェル)と組んで、ヒップホップの要素を取り入れたまったく新しいサウンドを提示し、音楽シーン全体に衝撃を与えた。
そして80年代後半になり、フュージョンも新しい時代を迎える。マイルス復帰後の“マイルス・スクール”の卒業生たち、マーカス・ミラー、マイク・スターン、ジョン・スコフィールド、ボブ・バーグ、ビル・エヴァンス、ロバート・アーヴィング、アダム・ホルツマン、ケイ赤城などといったミュージシャンたちがマイルスから学んだものを独自のサウンドとして展開し、特にマーカス・ミラーはポップスとジャズを見事にブレンドし、まったく新しいサウンドを作り上げていった。またそれ以外のミュージシャンたちも、例えばラリー・カールトンはアコースティック・ギターをフィーチュアしたサウンドで人気を得、リー・リトナーとデイヴ・グルーシンは『ハーレクイン』でブラジリアン・ポップスを見事にフュージョン・サウンドに取り入れることに成功し、そしてチック・コリアは才能ある若いミュージシャンたち結集させて“チック・コリア・エレクトリック・バンド”を結成したりして、いずれも若いファン層を獲得していった。またパット・メセニーはその類い希なる感性でまったくオリジナルな音楽を作り出し、ポピュラーな人気を獲得している。またスティーヴ・コールマンやジョン・ゾーンなどような、いわゆるフュージョンとはちょっと違うが、様々な音楽の要素を取り入れたまったく新しい方法論のジャズを展開するミュージシャンたちも登場してきた。
そしてケニー・G、ラス・フリーマン(リッピントンズ)、デヴィッド・ベノワ、カーク・ウェイラム、ジェラルド・アルブライト、スコット・ヘンダーソン、デニス・チェンバース、ジム・ベアード、キャンディ・ダルファー、ロニー・ジョーダンなどといった、フュージョンを聴いて育った世代、いわばフュージョン第2世代のミュージシャンたちが登場してくる。彼らはジャズもロックもブラック・ミュージックも何のこだわりもなく聴き、プレイし、必要とあれば彼らの音楽に最新のテクノロジーを積極的に取り入れる。つまり真の意味での“フュージョン・ミュージシャン”だといえる。そして90年代に入ると、フュージョンは、耳あたりが良く、よりソフィスティケイトされた“スムース・ジャズ”というひとつの流れを生み出し、ケニー・Gを筆頭に、ボニー・ジェイムス、ポール・ブラウン、リック・ブラウン、ウォルター・ビーズリーなどといった、新しいスターたちを次々と生み出していった。
そしてもうひとつ特筆すべきことは、70年代フュージョンのスターだったミュージシャンたちの多くが現在も第一線で活躍し、しかも彼らは基本的に当時の音楽を彼らなりに発展させたサウンドをクリエイトして、それが若いファンにもアピールしているのだ。その最もいい例が、ボブ・ジェイムス、リー・リトナー(後にラリー・カールトン、チャック・ローブと交代)、ハーヴィ・メイソン、ネイザン・イーストによる“フォー・プレイ”だろう。彼らは成熟した、まさに“90年代のフュージョン”ともいうべきサウンドをクリエイトし、大きな人気を得ている。
70年代にフュージョンを作り出したミュージシャンたちは、流行を追いかけていたのではなく、自分たちの信念で新しい音楽にチャレンジしていったのである。そして彼らの挑戦は今も続いているのだ。そう、そのスピリッツこそ、“ジャズ”そのものなのである。かつて“ジャズ=自由”というスピリットを実践していたのはマイルス・デイヴィスであり、チャーリー・パーカーであり、デューク・エリントンであり、セロニアス・モンクであり、チャールズ・ミンガスだった。そんな彼らの“自由なスピリット”は、フュージョン・ミュージシャンたちの中にも確実に息衝いているのである。だからこそもう一度、“フュージョン”という音楽を再評価してみたい。フュージョンはこんなにも熱く、真摯で、自由で、魅力的な音楽なのである。
(text by Yoshihiro "KUMA" Kumagai)
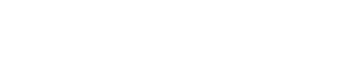

ⓒ 熊谷美広 (Yoshihiro Kumagai)